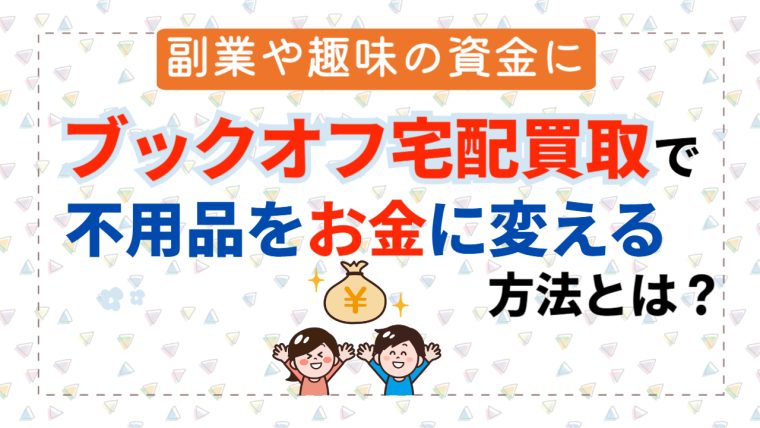【戦後80年】なぜ今、空前のベストセラー『流れる星は生きている』(藤原てい著)を読むべきなのか

今年の2025年は戦後80年という、歴史の大きな節目を迎えます。
この特別な年に、戦後の日本で空前の大ベストセラーとなり、今なお多くの人々に読み継がれている壮絶なノンフィクション、藤原てい著『流れる星は生きている』をご紹介します。
なぜ今、この本が私たちの心に響くのか。その理由を紐解いていきたいと思います。
『流れる星は生きている』(藤原てい著)とは
『流れる星は生きている』は、戦後の大ベストセラーとなった壮絶なノンフィクションです。
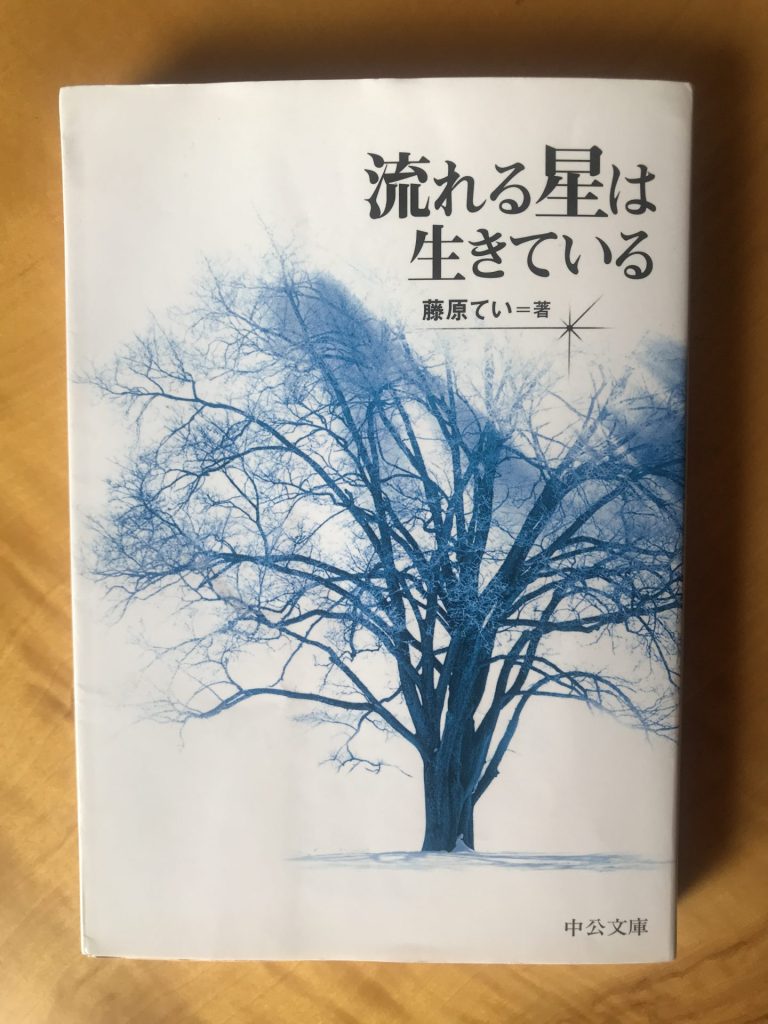
初版は1949年に日比谷出版社より刊行され、これまで複数の出版社から版を重ねて出版されています。
著者の藤原ていさんの夫は、作家の新田次郎さん。
数学者でエッセイストの藤原正彦さんのお母様です。
のちに作家となる新田次郎氏と結婚した著者は、満州国の首都であった新京(現在の長春)の観象台に赴任する夫とともに満州に渡ります。
この本は、終戦間際の満州で、ソ連軍の侵攻によって突然の避難を余儀なくされた著者が、幼い3人の子どもたちを連れ、夫(新田次郎)と離ればなれになりながら、決死の覚悟で日本への帰国を目指し、新京から朝鮮半島を陸路南下して生き抜いた壮絶な記録です。
飢え、寒さ、恐怖に耐えながら、幾度となく死の淵をさまよいます。
私は中公文庫で読んでいます。
中公文庫版は1976年初版発行、2002年に改訂版が発行されています。
私が持っている本の奥付を見ると、2002年改訂、改版14刷となっています。
文字サイズは一般的な文庫本とほぼ同じくらいで、シニア世代の私ですが、文字が小さくて読みにくい、と感じることはありませんでした。
一般的な文庫本と同じくらいの文字の大きさかと思います。
戦争体験世代の母が私に託した本
実家の母は、子ども時代に戦争を体験しています。
その母から「この本は絶対に読んだ方がいい」と強く勧められたのがきっかけでした。
それで早速、文庫本を購入しました。
言語に絶する緊迫感。
追い詰められたとき、人間はどうなるのか?
そのリアルな描写に、心底驚かされました。
戦争を知るための本はたくさん出版されています。
軍事作戦や軍隊での生活、戦況、当時の国際関係を描く本とは違い、この本には一人の女性と3人の子どもがたどった「命がけの旅」が克明に描かれています。
あたりまえの日常。あたり前の生活。
そんな「あたり前」が、一瞬にして非日常の壮絶な日々に変わってしまう。
その歴史の真実に、底知れない恐ろしさを感じます。
遠い過去の出来事ではない。
私たちの身近に起こりえる話しなのだと、改めて胸に刻まれました。
極限状態で人はどうなるのか?
この本を読んで強く感じたのは、極限状態に置かれた人間の「本性」です。
暗闇で自分の子どもの顔さえわからない風雨の中、右手に次男を抱きかかえ、左手に長男の手を持ち、娘を背負い、リュックを首にかけて、赤土の泥の中をもがきながら進みます。
「しいッ!」
という男の声がどこからか聞こえてきた。
「これから最も危険の場所を夜中(よるじゅう)歩きます。出来るだけ荷物を軽くして前の人を見失わないように急いで歩くのです。すぐ出発します。すぐ出発します!」
その声は風雨の中に低く恐ろしいひびきを持って伝わって来た。
「列から離れた人は置いて行かれますよ。前の人を見失わないように、落伍したらおしまいですよ」(中略)
黒い人の群の後をおくれまいおくれまいとついて行った。町を出て山道にかかった。赤土の泥道である。列は自然と長い線になり私は末端にいて、後をついてきしてくるものを感じながら、逃げていく日本人全体の最も苦しい精神的重荷を一人で背負わなければならないようであった。私は時々暗闇を振り返って見た。いつも嵐が私を追いかけているだけであった。
「逃げるんだ逃げるんだ。逃げおくれると私たちは殺される」
私は三八度線まで、こう心を叱咤しながら歩いた。(出典:『流れる星は生きている』藤原てい著/中公文庫)
凍てつく道で倒れた隣人を、置き去りにせざるをえないこともある。
いつも人に優しい人が、極限状態では自分のことを真っ先に考える人に変わってしまうこともある。
そうかと思うと、自分の命を削ってまで、他者に優しさを与え続ける人もいる。
極限状況に置かれたときの、善悪だけでは計り知れない、人間の心の深さと複雑さや、
どんな状況でも揺るがない人間の本心ということについて、深く考えさせられるのです。
妻の成功が夫を動かした!~新田次郎誕生秘話~
そしてもうひとつ、私の心に残ったのは、著者がベストセラー作家になった後のエピソードがあります。
藤原ていさんの本をもっと読みたくなり、エッセイ集『旅路』を読みました。
そうしたらこれがまた、別の意味での衝撃があったんです。
突然ベストセラー作家となった藤原ていさん。
『流れる星は生きている』発売は昭和24年ということなので、当時は家庭の奥様が外でお仕事されるのは珍しかったでしょう。
家のことをきちんとすることを条件に、夫さんから作家活動の了解を得ていたそうです。
やっとの思いで満洲から帰国して、家族一緒に暮らせるようになったというのに、妻の大活躍のそばで、「家事をきちんとすれば仕事をしていい」と言いながら、夫は不機嫌だったそうです。
家では口もきかず、家族で囲む食卓は暗い雰囲気になり、食事をするとすぐ自分の部屋に引きあげていたようです。
そんな生活が1年も続いたある日のこと。
いつものように自室に引きあげた夫さんが、階段をどんどんいわせて居間に戻ってきた。
そしてちゃぶ台にバンッと雑誌をたたき置いたそうです。
そして「俺だってやればできるんだ」と叫んだそうなんです。
その雑誌には夫さんの作品が掲載されていました。
作家・新田次郎の誕生です。
このエピソードを知った時、妻への嫉妬や悔しさが、直木賞作家「新田次郎」を生み出すきっかけになったのだと知って、なんだか微笑ましく感じました。
新田次郎さんの本名は藤原 寛人(ふじわら ひろと)さんです。
1956年『強力伝』で直木賞受賞。
代表作に『八甲田山死の彷徨』『孤高の人』『劔岳 点の記』などの山岳小説があります。
『八甲田山死の彷徨』は明治35年に起きた日本陸軍の雪中行軍で、訓練への参加者210名中199名が死亡するという、日本の冬季訓練における最も多くの死傷者の出てしまった事故をモチーフにして描かれています。
日清戦争で冬の寒冷地での苦戦を強いられた日本陸軍は、対ロシア戦に向けて雪中訓練をしていたのです。
また、『武田信玄』『武田勝頼』など歴史小説でも大きな足跡を残しています。
『八甲田山死の彷徨』は「八甲田山」のタイトルで映画化されました。
1977年(昭和52年)に公開されると、日本映画歴代配収新記録を打ち立てる大ヒットとなりました。
八甲田山中で方向もわからず猛吹雪にさらされて、もうだめだと思った北大路欣也さん扮する大尉が「天は我々を見放した」と咆哮するシーンは強烈なインパクトがありました。学校でもみんなの話題になっていたことをよく覚えています。
まとめ
今回の記事では、戦後空前のベストセラー『流れる星は生きている』(藤原てい著)をご紹介しました。
『流れる星は生きている』は、戦争の記録ということだけではありません。
戦争の悲惨さや言語に絶する苦難だけでなく、その中で見出される人間の強さ、精神性、心のあり方を考えるきっかけを与えてくれる一冊だと思います。
2025年は「戦後80年」という節目の年です。
『流れる星は生きている』は80年前に本当にあった話です。
戦争を経験した世代は少なくなり、直接に話を聞く機会はなくなってきていきます。
戦争を直接知らない世代が増えている今だからこそ、私たちはこの物語を読み継いでいく必要があるのではないでしょうか。
ぜひ、この機会に手に取ってみませんか。
ブログランキングに参加しています
にほんブログ村 FC2 Blog Ranking